新社会人の皆さん、電話応対に不安を感じていませんか。ビジネスシーンでの電話は、会社の顔としての対応が求められるため、緊張する場面も多いでしょう。特に、クレームや間違い電話など、イレギュラーな状況にどう対応すれば良いのか、戸惑うこともあるかもしれません。この記事では、新卒社員が困りがちな電話応対の状況と、その解決策を具体的に解説します。
電話をかける前に確認すべき準備とは
用件を整理する:簡潔に伝えるために
電話をかける前に、まず用件を整理しましょう。何を伝えたいのか、結論から先に考えることが大切です。例えば、会議の日程調整であれば、「〇月〇日の会議の件でご連絡いたしました」と最初に伝え、その後、具体的な日時や場所などの詳細を伝えるようにします。このように用件を整理することで、相手に要点が伝わりやすくなり、スムーズな会話につながります。
具体例として、Aさんが取引先のBさんに新商品の紹介で電話をかける場合を考えてみましょう。Aさんは、まず「新商品〇〇のご紹介でご連絡いたしました」と伝え、その後、商品の特徴や価格、納期などを説明します。さらに、Bさんの興味を引くような具体的なメリットを提示できれば、商談につながる可能性も高まります。事前にしっかりと情報を整理し、相手に伝えるべきポイントを明確にしておくことが、効果的な電話応対の第一歩です。
このように、用件を整理し、簡潔に伝える準備を整えておくことで、相手も内容を理解しやすくなり、スムーズなコミュニケーションを実現できます。
必要な資料を準備する:スムーズな会話のために
電話中に必要な資料を手元に準備しておくことも重要です。例えば、商品の価格表、顧客情報、過去の取引履歴など、会話中に参照する可能性のある資料は、すぐに取り出せるようにしておきましょう。これにより、相手を待たせることなく、スムーズに情報を提供できます。
例えば、あなたがお客様から製品の価格について問い合わせを受けたとします。手元に価格表があれば、すぐに正確な金額を伝えることができます。もし価格表が見当たらず、探すのに時間がかかってしまうと、お客様を待たせてしまい、会社の信頼を損ねる可能性もあります。事前に必要な資料を準備しておくことは、お客様への迅速な対応、ひいては顧客満足度向上につながるのです。
事前に会話の内容を予測し、関連資料を手元に揃えておくことで、落ち着いて対応できるだけでなく、相手にも安心感を与えられます。
相手の情報を確認する:失礼のない対応のために
電話をかける前に、相手の会社名、部署名、役職、氏名などを確認しましょう。特に、初めて電話をかける相手の場合は、失礼のないよう、事前に情報を調べておくことが大切です。会社のホームページや名刺交換をした際の記録などを参考に、正確な情報を把握しておきましょう。
例えば、初めて連絡する相手に電話をかける際、相手の名前を間違えてしまうと、非常に失礼な印象を与えてしまいます。また、部署名や役職を間違えると、たらい回しにされたり、適切な担当者につないでもらえなかったりする可能性もあります。事前に相手の情報を確認しておくことは、スムーズなコミュニケーションの第一歩であり、ビジネスマナーの基本です。
ちなみに、相手の会社の代表電話番号しか分からない場合は、電話に出た方に「〇〇部の〇〇様をお願いします」と伝えれば、取り次いでもらえます。部署名が分からない場合は、「〇〇についてお伺いしたいのですが、ご担当の方はいらっしゃいますか」などと尋ねると良いでしょう。
相手の情報を事前に確認し、失礼のない対応を心がけることが、良好な関係を築くための第一歩となります。それでは次に、電話応対の基本ステップを見ていきましょう。
電話応対の基本ステップ:失礼のない第一印象のために
挨拶と名乗り:相手に安心感を与える
電話に出たら、まず明るくハキハキと挨拶し、会社名と自分の名前を名乗りましょう。「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社の〇〇です」というように、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。最初の挨拶は、相手に与える第一印象を大きく左右します。明るく丁寧な挨拶は、相手に安心感を与え、その後の会話をスムーズに進めるための土台となります。
例えば、あなたがお客様からの電話を受けたとします。「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社の△△です」と名乗ると、お客様は「〇〇株式会社の△△さん」という情報を得て、安心して要件を話し始めることができます。もし、会社名も名前も名乗らずに「はい」とだけ応答すると、お客様は「本当にこの会社で合っているのだろうか」「誰が電話に出ているのだろうか」と不安に感じてしまうかもしれません。
相手に安心感を与える挨拶と名乗りは、信頼関係を築くための重要な要素です。
用件の伝達:明確かつ丁寧に
挨拶と名乗りを終えたら、用件を明確かつ丁寧に伝えましょう。結論を先に述べ、その後で詳細を説明するようにすると、相手に伝わりやすくなります。また、早口になったり、専門用語を多用したりすることは避け、相手の理解度に合わせて話すことが大切です。
例えば、商品の納期について問い合わせる場合、「〇〇の納期についてお伺いしたいのですが」と最初に用件を伝えます。その後、「〇月〇日に注文した〇〇の納期はいつになりますでしょうか」と具体的な情報を伝えると、相手も状況を把握しやすくなります。もし、最初に「〇月〇日に注文した商品があるのですが…」と話し始めると、相手は何の用件か分からず、戸惑ってしまうかもしれません。
用件を明確に伝えることで、相手との認識のずれを防ぎ、スムーズなコミュニケーションを実現できます。
相手の状況を確認する:配慮を示す
用件を伝える前に、相手の状況を確認することも大切です。「〇〇様、今お時間よろしいでしょうか」などと一声かけることで、相手に配慮を示すことができます。もし、相手が忙しいようであれば、「改めてこちらからお電話いたします」と伝え、後ほどかけ直すようにしましょう。
例えば、あなたが取引先の担当者に電話をかけたとします。「〇〇様、今お時間よろしいでしょうか」と尋ねると、相手は「今は少し忙しいので、後でかけ直してほしい」とか、「5分程度なら大丈夫です」などと答えてくれるでしょう。これにより、相手の状況に合わせて対応することができ、失礼な印象を与えることを避けられます。
相手の状況を確認し、配慮を示すことで、相手との良好な関係を築くことができます。
それでは、次はアポイントメントの取り方について、具体的なポイントを見ていきましょう。
アポイントメントの取り方:成功への3つのポイント
希望日時を提示する:具体的な提案をする
アポイントメントを取る際は、まず、具体的な希望日時を提示しましょう。「〇月〇日の〇時はいかがでしょうか」というように、具体的な日時を提案することで、相手も予定を確認しやすくなります。漠然と「いつがよろしいでしょうか」と尋ねるよりも、具体的な日時を提示する方が、相手に負担をかけずに済みます。
例えば、あなたがお客様に新商品の説明をするためにアポイントメントを取りたいとします。「〇月〇日の〇時、または〇月△日の△時はいかがでしょうか」と複数の候補日を提示すると、お客様は自分のスケジュールと照らし合わせて、都合の良い日時を選ぶことができます。もし、「いつがよろしいでしょうか」とだけ尋ねると、お客様は「いつが良いだろうか」と考える時間が必要になり、返答に時間がかかってしまうかもしれません。
具体的な希望日時を提示することは、スムーズなアポイントメント取得に不可欠です。
代替案を提示する:柔軟性を示す
最初に提示した日時が相手の都合に合わない場合に備えて、代替案をいくつか用意しておきましょう。「もし、〇月〇日が難しいようでしたら、〇月△日はいかがでしょうか」というように、柔軟に対応できる姿勢を示すことが大切です。これにより、相手に「自分の都合を考慮してくれている」という印象を与え、アポイントメントが成立しやすくなります。
例えば、あなたがお客様に提案した日時が、お客様の出張と重なってしまったとします。「〇月〇日は出張で不在にしております」と言われたら、「それでは、〇月△日はいかがでしょうか。もし、△日も難しいようでしたら、他の日程も調整いたします」と代替案を提示します。これにより、お客様は「自分の都合に合わせて調整してくれようとしている」と感じ、アポイントメントを受け入れやすくなるでしょう。
代替案を提示し、柔軟性を示すことで、相手との信頼関係を深めることができます。
相手の都合を優先する:誠実な姿勢を見せる
アポイントメントの日時を決める際は、相手の都合を最優先に考えましょう。「〇〇様のご都合の良い日時をいくつかお教えいただけますでしょうか」というように、相手に選択肢を委ねる姿勢を示すことが大切です。これにより、相手に「自分の都合を尊重してくれている」という印象を与え、良好な関係を築くことができます。
例えば、あなたがお客様にアポイントメントの候補日をいくつか提示したとします。「〇〇様のご都合の良い日時をいくつかお教えいただけますでしょうか」と尋ねると、お客様は「〇月〇日と△日なら大丈夫です」などと答えてくれるでしょう。これにより、お客様の都合に合わせたアポイントメントを設定でき、お客様の満足度を高めることができます。もし、一方的に日時を指定してしまうと、お客様は「自分の都合を無視された」と感じ、不快な思いをしてしまうかもしれません。
ちなみに、どうしても相手の都合がつかない場合は、上司に相談して、他の担当者に代わってもらうことも検討しましょう。
相手の都合を優先し、誠実な姿勢を見せることで、信頼関係を構築し、円滑なコミュニケーションを促進できます。 では次に、相手が不在の場合の対応について、具体的な方法を確認しましょう。
相手が不在の場合の対応:次につながる行動
伝言を依頼する:丁寧な言葉遣いを心がける
電話をかけた相手が不在の場合、伝言を依頼することができます。その際は、丁寧な言葉遣いを心がけ、用件を簡潔に伝えましょう。「〇〇の件でお電話いたしました。〇〇様にお伝えいただけますでしょうか」というように、失礼のないように伝言を依頼することが大切です。
例えば、あなたが取引先の担当者に電話をかけ、担当者が不在だったとします。「〇〇株式会社の△△と申します。〇〇様にお伝えいただきたいのですが、先日ご注文いただいた商品の納期が〇月〇日になる見込みです。お手数ですが、〇〇様にご伝言をお願いできますでしょうか」と伝えます。このように、用件を簡潔かつ丁寧に伝えることで、相手に負担をかけずに、正確な情報を伝えることができます。
伝言を依頼する際は、丁寧な言葉遣いを心がけ、相手に不快感を与えないように注意しましょう。
折り返しを依頼する:連絡先を明確に伝える
相手に折り返し電話を依頼する場合は、自分の会社名、部署名、氏名、電話番号を明確に伝えましょう。「〇〇株式会社の△△と申します。折り返しお電話をいただきたいのですが、電話番号は〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇です」というように、相手がスムーズに折り返し電話をかけられるように、必要な情報をすべて伝えることが大切です。
例えば、あなたが取引先の担当者に電話をかけ、担当者が不在だったとします。「〇〇株式会社の△△と申します。〇〇様から折り返しお電話をいただきたいのですが、電話番号は〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇です。〇〇の件でご連絡いたしました。お手数ですが、〇〇様にお伝えいただけますでしょうか」と伝えます。このように、連絡先を明確に伝えることで、相手からの折り返し電話を確実に受け取ることができます。
折り返しを依頼する際は、相手に負担をかけないよう、連絡先を明確に伝えることが重要です。
再度かけ直す:適切な時間帯を選ぶ
伝言や折り返しを依頼せず、再度かけ直す場合は、適切な時間帯を選びましょう。相手が忙しい時間帯や、昼休憩の時間を避けるなど、相手の状況を考慮することが大切です。また、「〇〇様はいらっしゃいますでしょうか」と尋ねる前に、「先ほどもお電話させていただいたのですが」と一言添えると、相手に状況が伝わりやすくなります。
例えば、午前中に電話をかけて相手が不在だった場合、午後にもう一度かけ直すことができます。その際、「〇〇株式会社の△△と申します。先ほどもお電話させていただいたのですが、〇〇様はいらっしゃいますでしょうか」と尋ねます。このように、再度かけ直す旨を伝えることで、相手も状況を理解しやすくなり、スムーズな対応が期待できます。
補足すると、何度もかけ直すと、相手に迷惑をかけてしまう可能性があります。何度か電話をしてもつながらない場合は、メールなど、他の連絡手段を検討することも考えましょう。
再度かけ直す際は、適切な時間帯を選び、相手に配慮することが大切です。それでは最後に、電話をかける時間帯のマナーについて確認しましょう。
電話をかける時間帯:ビジネスマナーを守る
始業直後や終業間際は避ける:相手の迷惑にならないように
電話をかける時間帯として、始業直後や終業間際は避けるのが一般的なビジネスマナーです。始業直後は、朝礼やメールチェックなどで忙しい場合が多く、終業間際は、退社準備や残業などで慌ただしい場合があります。これらの時間帯に電話をかけると、相手に迷惑をかけてしまう可能性があるため、避けるようにしましょう。
例えば、あなたが取引先に電話をかける場合、相手の会社の始業時間が9時であれば、9時30分以降に電話をかけるのが望ましいでしょう。また、終業時間が18時であれば、17時30分までに電話をかけるようにしましょう。これにより、相手に迷惑をかけることなく、スムーズなコミュニケーションを図ることができます。
相手の状況を考慮し、迷惑にならない時間帯に電話をかけることが、ビジネスマナーの基本です。
昼休憩の時間を避ける:相手のプライベートに配慮する
昼休憩の時間帯も、電話をかけるのを避けるのがマナーです。多くの企業では、12時から13時、または13時から14時を昼休憩としています。この時間帯は、食事や休憩を取っている人が多いため、電話をかけると迷惑になる可能性があります。緊急の用件でない限り、昼休憩の時間帯は避けるようにしましょう。
例えば、あなたが取引先に電話をかける場合、相手の会社の昼休憩が12時から13時であれば、13時以降に電話をかけるのが望ましいでしょう。これにより、相手のプライベートな時間を尊重し、良好な関係を維持することができます。
相手のプライベートに配慮し、昼休憩の時間を避けて電話をかけることが、ビジネスマナーとして重要です。
相手の会社の営業時間を考慮する:常識的な行動を
電話をかける際は、相手の会社の営業時間を考慮しましょう。営業時間外に電話をかけると、誰も電話に出ない可能性があります。また、営業時間内であっても、早朝や深夜など、常識的に考えて非常識な時間帯に電話をかけるのは避けましょう。
例えば、あなたが取引先に電話をかける場合、相手の会社の営業時間が9時から18時であれば、この時間内に電話をかけるのが基本です。もし、営業時間外に緊急の用件がある場合は、メールなど、他の連絡手段を検討しましょう。どうしても電話をかける必要がある場合は、「営業時間外に失礼いたします」と一言添えるのがマナーです。
ちなみに、相手の会社の営業時間が分からない場合は、会社のホームページで確認するか、代表電話に問い合わせて確認しましょう。相手の会社の営業時間を考慮し、常識的な行動を心がけることが、ビジネスマナーの基本です。
まとめ
今回は、新卒社員が困りがちな電話応対について、ケース別の対応方法と解決策を解説しました。電話をかける前の準備、基本ステップ、アポイントメントの取り方、不在時の対応、そして電話をかける時間帯のマナーなど、実践的な内容を盛り込みました。電話応対は、ビジネスマナーの基本であり、会社の顔としての対応が求められます。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、この記事で紹介した内容を参考に、落ち着いて、そして相手への配慮を忘れずに対応することで、徐々に自信を持って電話応対できるようになるでしょう。経験を積むほど、スムーズなコミュニケーションが可能になります。

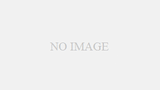
コメント