新卒で入社し、初めての電話応対にドキドキしているあなた。ビジネスシーンでの電話応対は、会社の顔としてお客様と接する大切な機会です。言葉遣い一つで、会社の印象が大きく左右されることもあります。この記事では、電話応対でよく使う敬語、クッション言葉、丁寧語などを網羅的に解説。電話応対の基本から、よくある間違い、より丁寧な表現への言い換えまで、具体例を交えながら徹底的にマスターしていきましょう。
電話応対の基本:あなたは大丈夫?最初の挨拶と名乗り方
第一印象を決める!電話応対の第一声、どうすれば良い?
電話応対の第一声は、あなたの、そして会社の印象を決定づける非常に重要なものです。「はい、〇〇株式会社でございます」と、明るくハキハキと名乗ることが基本です。声のトーンは、普段よりも少し高めを意識すると、相手に好印象を与えられます。例えば、普段「ド」の音で話しているとしたら、「レ」や「ミ」の音を意識すると、自然と明るい声になります。
ここで大切なのは、「もしもし」を使わないことです。「もしもし」は、ビジネスシーンではふさわしくありません。代わりに、「はい」と、はっきりとした返事を心がけましょう。例えば、あなたがお客様としてお店に電話をかけた時、「はい、〇〇(店名)です」と名乗られるのと、「もしもし?」と言われるのとでは、どちらが安心感を得られるでしょうか。多くの方が前者を選ぶはずです。電話応対は、相手に安心感と信頼感を与えることが大切です。
また、電話を受けた状況によっては、名乗りの前に一言添えることも有効です。例えば、朝であれば「おはようございます。〇〇株式会社でございます」、午後であれば「お世話になっております。〇〇株式会社でございます」といった具合です。時間帯や状況に合わせた挨拶を加えることで、より丁寧な印象を与えられます。これは、相手への気遣いを言葉で表現する、ちょっとしたテクニックです。
相手に安心感を与える。スムーズな名乗り方のコツとは
スムーズな名乗り方は、相手に安心感を与えるだけでなく、その後の会話を円滑に進めるための土台となります。まず、会社名を名乗る際は、正式名称を省略せずに伝えましょう。「〇〇株式会社」であれば、「〇〇(株)」ではなく、「〇〇かぶしきがいしゃ」と、はっきりと伝えます。早口になったり、語尾が不明瞭になったりしないように注意が必要です。
次に、自分の部署と名前を名乗ります。「営業部の山田太郎でございます」といった具合です。部署名を伝えることで、相手は誰と話しているのかを明確に理解できます。名前は、フルネームで名乗ることが基本です。これにより、相手はあなたを個人として認識し、より親近感を持つことができます。
例えば、あなたが病院に電話をかけたとします。「〇〇病院です」とだけ名乗られるのと、「〇〇病院、受付の山田です」と名乗られるのとでは、どちらが安心できるでしょうか。後者の方が、具体的な担当者がいることが分かり、安心感が増すはずです。電話応対も同様で、部署と名前を明確に伝えることが、相手への配慮となります。
万が一、相手の声が聞き取りにくい場合は、正直に伝えましょう。「恐れ入りますが、お電話が少々遠いようです。もう一度お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか」と、丁寧に聞き返すことが大切です。曖昧なまま会話を進めるよりも、きちんと確認することで、誤解やトラブルを防ぐことができます。
また、内線電話の場合は、部署名と名前を名乗るだけで構いません。「内線〇〇番、山田です」といった具合です。内線電話は、社内の人同士の通話なので、簡潔な名乗り方で問題ありません。ですから、スムーズな名乗り方は、相手に安心感を与える上で非常に大切です。
聞き取りやすい声で話すには?電話応対で意識すべきポイント
電話応対では、直接顔が見えない分、声のトーンや話し方が、相手に与える印象を大きく左右します。聞き取りやすい声で話すことは、相手への配慮であり、スムーズなコミュニケーションの基本です。
まず、意識したいのは、声のトーンと大きさです。普段よりも少し高めのトーンで、ハキハキと話すことを心がけましょう。低い声や小さな声は、相手に聞き取りにくく、暗い印象を与えてしまいます。例えば、あなたがラジオを聴いている時、DJの声が低く、ボソボソと話していたら、どう感じるでしょうか。おそらく、内容が頭に入ってこない、あるいは、番組自体に興味を失ってしまうかもしれません。電話応対も同じです。明るく、聞き取りやすい声で話すことが、相手に好印象を与えます。
次に、話すスピードにも注意が必要です。早口で話すと、相手は聞き取りにくく、焦っているような印象を受けてしまいます。反対に、ゆっくりと話しすぎると、相手をイライラさせてしまう可能性があります。適切なスピードは、相手の反応を見ながら調整することが理想的です。しかし、基本的には、普段よりも少しゆっくりと話すことを意識すると良いでしょう。
さらに、滑舌も重要なポイントです。言葉をはっきりと発音することで、相手はより聞き取りやすくなります。特に、数字や固有名詞は、間違えやすいので、注意が必要です。例えば、「1(いち)」と「7(しち)」、「B(ビー)」と「D(ディー)」などは、電話では聞き間違えやすい代表的な例です。これらの言葉を伝える際は、意識してはっきりと発音するようにしましょう。
補足すると、電話応対の前に、軽く声出しをすることも効果的です。簡単な発声練習や、早口言葉などを試してみると、滑舌が良くなり、声のトーンも安定します。電話応対は、声を使ったコミュニケーションです。聞き取りやすい声で話すことは、相手への配慮であり、信頼関係を築くための第一歩となります。
これらのポイントを意識して、電話応対の基本である、最初の挨拶と名乗り方をマスターすることで、自信を持って電話に出られるようになります。さて、次は、なぜ電話応対で敬語を使う必要があるのか、その理由と具体的な使い方について詳しく見ていきましょう。
なぜ重要?電話応対で敬語を使うべき3つの理由
敬語を使うメリットとは?顧客満足度向上のために
電話応対で敬語を使うことは、単なるマナーではなく、顧客満足度を向上させ、ひいては会社の利益に繋がる重要な要素です。敬語を使うことには、主に3つのメリットがあります。
1つ目は、相手に敬意を示すことができる点です。敬語は、相手を尊重し、丁寧な態度で接していることを示す言葉遣いです。お客様は、自分を大切に扱ってくれる会社に対して、好感を抱きます。例えば、あなたがお店で買い物をしている時、店員から丁寧な言葉遣いで接客されたら、どう感じるでしょうか。きっと、気持ち良く買い物ができ、またそのお店を利用したいと思うはずです。電話応対も同様で、敬語を使うことで、お客様に良い印象を与え、信頼関係を築くことができます。
2つ目は、会社の品格を高めることができる点です。社員一人ひとりの言葉遣いは、会社のイメージを大きく左右します。正しい敬語を使える社員が多い会社は、それだけで「しっかりとした会社」という印象を与えられます。逆に、言葉遣いが乱れている社員が多い会社は、「だらしない会社」という印象を持たれてしまう可能性があります。
3つ目は、トラブルを未然に防ぐことができる点です。敬語は、相手との間に適切な距離感を保ち、円滑なコミュニケーションを促進する効果があります。特に、クレーム対応など、難しい状況においては、敬語を使うことで、相手の感情を鎮め、冷静な話し合いを促すことができます。例えば、あなたがお客様からクレームを受けた場合、友達言葉で対応するのと、丁寧な敬語で対応するのとでは、どちらが相手の怒りを鎮めやすいでしょうか。多くの場合、後者の方が、事態を悪化させずに済むはずです。
したがって、敬語を使うことは、顧客満足度を向上させ、会社の信頼性を高め、トラブルを未然に防ぐという、3つの大きなメリットをもたらします。つまり、敬語は、ビジネスを円滑に進めるための「潤滑油」のようなものです。
敬語の種類を理解しよう。尊敬語・謙譲語・丁寧語の違い
敬語には、大きく分けて「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」の3種類があります。それぞれの違いを理解し、状況に応じて使い分けることが、ビジネスシーンでは求められます。
尊敬語は、相手の行動や状態を高めて表現する言葉です。相手に敬意を示すために使われます。例えば、「言う」の尊敬語は「おっしゃる」、「食べる」の尊敬語は「召し上がる」、「行く」の尊敬語は「いらっしゃる」です。お客様や目上の人に対して使うのが基本です。
謙譲語は、自分の行動や状態をへりくだって表現する言葉です。自分を低めることで、相対的に相手を高め、敬意を示すために使われます。例えば、「言う」の謙譲語は「申す」、「食べる」の謙譲語は「いただく」、「行く」の謙譲語は「参る」です。自分の行動について話す際に使います。
丁寧語は、言葉遣いを丁寧にする言葉です。相手や状況に関わらず、広く使うことができます。例えば、「です」「ます」「ございます」などが丁寧語にあたります。丁寧語は、尊敬語や謙譲語と組み合わせて使うこともできます。
例を挙げてみましょう。お客様に「どちらに行かれますか?」と尋ねる場合、「どちら」は中立的な言葉ですが、「行かれますか」は「行く」の尊敬語「行かれる」に丁寧語の「ます」を付けた形です。より丁寧に言うなら、「どちらへいらっしゃいますか?」となります。これは、「行く」の尊敬語「いらっしゃる」に丁寧語の「ますか」を付けた形です。
一方、自分がどこかへ行くことを伝える場合は、「明日、〇〇へ参ります」と言います。これは、「行く」の謙譲語「参る」に丁寧語の「ます」を付けた形です。このように、尊敬語・謙譲語・丁寧語を適切に使い分けることで、より丁寧で、相手に配慮した言葉遣いができるようになります。ですから、敬語の種類を理解し使い分けることは、相手に不快感を与えないために重要です。
ビジネスシーンで必須。状況に応じた敬語の使い分け方
敬語は、相手や状況に応じて使い分けることが重要です。社内、社外、お客様、上司など、相手によって適切な敬語は異なります。また、電話、メール、対面など、コミュニケーションの手段によっても、使い分ける必要があります。
社内での電話応対では、基本的に丁寧語を使います。上司に対しては、尊敬語や謙譲語を適切に使い分ける必要があります。例えば、上司に「〇〇部長は、いらっしゃいますか?」と尋ねられたら、「〇〇部長は、ただいま席を外しております」と答えます。この場合、「いる」の尊敬語「いらっしゃる」と、「席を外している」という丁寧な表現を使っています。
社外からの電話応対では、相手がお客様である場合、尊敬語と謙譲語を使い、最大限の敬意を示す必要があります。例えば、「〇〇様でいらっしゃいますか」「〇〇様がおっしゃる通りでございます」「弊社では、〇〇と申しております」といった具合です。
お客様からの電話で、担当者が不在の場合、「〇〇は、ただいま席を外しております。〇〇(時間)に戻る予定でございます」と、担当者の名前を呼び捨てにし、不在の理由と戻り時間を伝えます。これは、社内の人間である担当者を、お客様よりも低い立場として表現する謙譲語の考え方に基づいています。しかし、最近では、社内の人間であっても「さん」付けで呼ぶ会社も増えています。
補足すると、電話応対だけでなく、メールや対面でのコミュニケーションにおいても、敬語の使い分けは重要です。メールでは、より丁寧な言葉遣いを心がけ、顔文字や絵文字の使用は避けるべきです。対面では、言葉遣いだけでなく、表情や態度にも気を配る必要があります。相手の目を見て、笑顔で話すことを心がけましょう。
状況に応じた敬語の使い分けは、一朝一夕に身につくものではありません。日々の業務の中で、意識して使い続けることで、徐々に身についていきます。ですから、積極的に敬語を使うように意識し、少しずつステップアップしていきましょう。さて、次は、電話応対でよく使うフレーズを、具体的なケース別に見ていきましょう。
もう迷わない!電話応対でよく使うフレーズ集:実践編
電話を受ける時、何と言う?ケース別フレーズ集
電話を受ける時の最初のフレーズは、会社の印象を左右する重要なものです。状況に合わせて、適切なフレーズを使い分けましょう。
基本のフレーズは、「はい、〇〇株式会社でございます」です。明るく、ハキハキと名乗りましょう。会社の代表として電話に出ているという意識を持つことが大切です。
午前中(およそ10時頃まで)であれば、「おはようございます。〇〇株式会社でございます」と、挨拶を加えるのも良いでしょう。時間帯に合わせた挨拶は、相手に好印象を与えます。
相手が名乗った場合は、「〇〇様、いつもお世話になっております」と、相手の名前を復唱し、感謝の言葉を伝えます。相手の名前を呼ぶことで、親近感が湧き、その後の会話がスムーズに進みやすくなります。
例えば、取引先の〇〇株式会社の山田様から電話がかかってきた場合、「〇〇株式会社の山田様、いつもお世話になっております」と応対します。もし、初めて電話をかけてきた相手であれば、「〇〇株式会社の山田様、お電話ありがとうございます」と、感謝の気持ちを伝えるのも良いでしょう。
また、電話が少し遠い場合は、「恐れ入りますが、お電話が少々遠いようでございます。もう一度お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか」と、丁寧に聞き返しましょう。聞き取れないまま会話を進めるよりも、きちんと確認することが大切です。
このように、電話を受ける時のフレーズは、状況によって様々です。しかし、どのような場合でも、明るく、丁寧に、そして相手への配慮を忘れずに応対することが重要です。ですから、基本フレーズをしっかりと覚え、どんな状況でも対応できるようにしておきましょう。
相手に用件を尋ねるには?失礼のない聞き方
相手の用件を尋ねる際は、失礼のないように、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。相手に不快感を与えずに、スムーズに用件を聞き出すことが、ビジネスコミュニケーションの基本です。
基本のフレーズは、「恐れ入りますが、どのようなご用件でしょうか」です。「恐れ入りますが」というクッション言葉を使うことで、丁寧な印象を与えられます。また、「ご用件」という言葉を使うことで、相手の用件を尊重していることを示すことができます。
より丁寧な表現としては、「恐れ入りますが、ご用件を承ってもよろしいでしょうか」があります。「承る」は「聞く」の謙譲語であり、相手に敬意を示すことができます。
例えば、あなたがお客様から電話を受け、「〇〇の件で」とだけ言われた場合、「恐れ入りますが、〇〇の件について、詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか」と尋ねることができます。このように、具体的な内容を尋ねることで、相手も話しやすくなります。
また、相手が担当者を指名している場合は、「〇〇は、ただいま席を外しております。よろしければ、ご用件を承りますが、いかがでしょうか」と、担当者の不在を伝え、自分が対応できるかどうかを確認します。この時、「よろしければ」というクッション言葉を使うことで、相手に選択肢を与え、丁寧な印象を与えることができます。
補足すると、相手の用件を聞き出す際は、相槌を打ちながら、相手の話をしっかりと聞くことが大切です。「はい」「ええ」「さようでございますか」など、適切な相槌を打つことで、相手は安心して話すことができます。また、相手の話を遮ったり、否定したりすることは避けましょう。相手の用件を正確に把握するためには、傾聴の姿勢が重要です。
相手に失礼のない聞き方をマスターし、スムーズなコミュニケーションを実現してください。
電話を取り次ぐ/担当者が不在の場合、どう伝える?
電話を取り次ぐ場合や、担当者が不在の場合は、相手に失礼のないように、丁寧かつ適切な対応が求められます。会社の印象を損ねないためにも、正しい言葉遣いと対応を身につけましょう。
担当者に取り次ぐ場合は、まず「〇〇(担当者名)ですね。少々お待ちください」と伝え、保留にします。保留にする際は、「恐れ入りますが、少々お待ちいただけますでしょうか」と、クッション言葉を使うと、より丁寧な印象になります。
保留を解除する際は、「お待たせいたしました。〇〇(担当者名)にかわります」と伝えます。保留時間が長くなってしまった場合は、「大変お待たせいたしました」と、お詫びの言葉を添えましょう。
担当者が不在の場合は、その旨を丁寧に伝え、適切な対応を取る必要があります。例えば、「〇〇(担当者名)は、ただいま席を外しております。よろしければ、ご用件を承りますが、いかがでしょうか」と伝えます。「よろしければ」というクッション言葉を使うことで、相手に選択肢を与え、丁寧な印象を与えることができます。
もし、相手が伝言を希望する場合は、「〇〇(担当者名)に申し伝えます。恐れ入りますが、お名前とご連絡先をお伺いしてもよろしいでしょうか」と、伝言内容を正確に記録します。復唱し、間違いがないか確認することも大切です。
相手が折り返し電話を希望する場合は、「〇〇(担当者名)から折り返しお電話を差し上げるようにいたします。恐れ入りますが、お名前とご連絡先をお伺いしてもよろしいでしょうか」と伝えます。折り返し電話をする時間帯の希望があるかどうかも確認すると、より丁寧です。
補足すると、担当者が不在の場合、理由を詳しく説明する必要はありません。「席を外している」「外出している」といった、一般的な表現で十分です。ただし、お客様から「いつ戻りますか?」と尋ねられた場合は、「〇〇時頃に戻る予定です」と、具体的な時間を伝えるようにしましょう。但し、確実に戻る時間が分からない場合は、「戻り次第、折り返しお電話を差し上げるようにいたします」と伝えるのが無難です。
電話の取り次ぎや、担当者不在時の対応は、会社の印象を大きく左右します。これらの対応をスムーズに行えるようになれば、電話応対スキルは格段に向上します。次は、電話応対でさらに差をつける「クッション言葉」の活用術について詳しく見ていきましょう。
これで完璧!電話応対で差がつく「クッション言葉」活用術
クッション言葉とは?相手への配慮を示す魔法の言葉
クッション言葉とは、言葉の前に添えることで、直接的な表現を避け、相手への配慮を示すことができる言葉です。電話応対では、クッション言葉を効果的に使うことで、より丁寧で、相手に好印象を与えられます。
クッション言葉は、相手に何かをお願いする時、断る時、反論する時など、様々な場面で使うことができます。例えば、「恐れ入りますが」「よろしければ」「失礼ですが」「申し上げにくいのですが」などがあります。
「恐れ入りますが」は、相手に何かをお願いする時や、尋ねる時によく使われます。「恐れ入りますが、〇〇様はいらっしゃいますか」「恐れ入りますが、ご用件を承ってもよろしいでしょうか」といった具合です。この言葉を使うことで、相手に敬意を示し、丁寧な印象を与えられます。
「よろしければ」は、相手に何かを提案する時や、選択肢を与える時によく使われます。「よろしければ、私がご用件を承りますが、いかがでしょうか」「よろしければ、〇〇(商品名)について、詳しくご説明いたしますが、いかがでしょうか」といった具合です。この言葉を使うことで、相手に選択の自由を与え、押し付けがましい印象を避けることができます。
「失礼ですが」は、相手に何かを確認する時や、反対意見を述べる時によく使われます。「失礼ですが、〇〇様でいらっしゃいますか」「失礼ですが、その件については、〇〇(別の意見)と考えます」といった具合です。この言葉を使うことで、相手に不快感を与えずに、自分の意見を伝えることができます。
これらのクッション言葉は、電話応対だけでなく、日常会話やビジネスシーン全般で活用できます。言葉の前に一言添えるだけで、相手への配慮を示すことができる「魔法の言葉」と言えるでしょう。つまり、クッション言葉を適切に使うことは、相手に安心感を与えられます。
どんな時に使う?クッション言葉の具体的な使用例
クッション言葉は、様々な場面で活用できます。具体的な使用例を知ることで、より効果的に使いこなせるようになります。
【依頼】
相手に何かをお願いする時は、「恐れ入りますが」「よろしければ」「お手数をおかけしますが」などのクッション言葉を使います。
例:「恐れ入りますが、〇〇の資料をお送りいただけますでしょうか」
「よろしければ、〇〇について、詳しく教えていただけますでしょうか」
「お手数をおかけしますが、〇〇の件、ご確認いただけますでしょうか」
【確認】
相手に何かを確認する時は、「失礼ですが」「念のためお伺いしますが」「差し支えなければ」などのクッション言葉を使います。
例:「失礼ですが、〇〇様でいらっしゃいますか」
「念のためお伺いしますが、〇〇ということでよろしいでしょうか」
「差し支えなければ、〇〇について、お聞かせいただけますでしょうか」
【反論】
相手に反対意見を述べる時は、「失礼ですが」「申し上げにくいのですが」「恐縮ですが」などのクッション言葉を使います。
例:「失礼ですが、その件については、〇〇(別の意見)と考えます」
「申し上げにくいのですが、〇〇の点については、改善の余地があるかと存じます」
「恐縮ですが、〇〇の件、もう一度ご検討いただけますでしょうか」
【お断り】
相手の依頼を断る時は、「申し訳ございませんが」「あいにくですが」「せっかくですが」などのクッション言葉を使います。
例:「申し訳ございませんが、その日は都合がつきません」
「あいにくですが、〇〇(商品名)は、ただいま在庫を切らしております」
「せっかくですが、今回は見送らせていただきます」
補足すると、クッション言葉は、多用しすぎると、かえってくどい印象を与えてしまうことがあります。状況に応じて、適切なクッション言葉を、適切なタイミングで使うことが大切です。ですから、相手や状況に合わせて、最適なクッション言葉を選び、効果的に活用しましょう。
より丁寧な印象に。クッション言葉+αのテクニック
クッション言葉は、単独で使うだけでなく、他の言葉と組み合わせることで、より丁寧な印象を与えられます。
例えば、「恐れ入りますが」の後に、「少々お待ちいただけますでしょうか」と続けることで、相手に待ってもらうことをお願いする表現が、より丁寧になります。「恐れ入りますが、少々お待ちいただけますでしょうか。〇〇(担当者名)にかわります」といった具合です。
また、「よろしければ」の後に、「ご検討いただけますでしょうか」と続けることで、相手に何かを検討してもらうことをお願いする表現が、より丁寧になります。「よろしければ、〇〇(商品名)について、ご検討いただけますでしょうか」といった具合です。
さらに、「申し上げにくいのですが」の後に、「〇〇の点については、ご理解いただけますと幸いです」と続けることで、相手に理解を求める表現が、より丁寧になります。「申し上げにくいのですが、〇〇の点については、ご理解いただけますと幸いです」といった具合です。
クッション言葉に、さらに別の丁寧な表現を付け加える、合わせ技のテクニックです。例えば「よろしければ」に「ご検討ください」を丁寧にした「ご検討いただけますでしょうか」を付け加えることで、より丁寧な表現に変わります。これは、相手への敬意を、より強く表現するためのテクニックです。
ちなみに、クッション言葉と似た効果を持つ言葉として、「お言葉ですが」「おっしゃる通りですが」などがあります。これらは、相手の意見を一度受け止めた上で、自分の意見を述べる際に使うことができます。例えば、「お言葉ですが、〇〇の点については、〇〇(別の意見)と考えます」「おっしゃる通りですが、〇〇の点については、別の見方もできるかと存じます」といった具合です。
クッション言葉+αのテクニックをマスターし、電話応対スキルをさらに向上させてください。次は、電話応対でよくある間違いと、その改善策について見ていきましょう。
電話応対の言葉遣い:よくある間違いと改善策をチェック
「了解しました」はNG?ビジネスシーンにふさわしい表現へ
「了解しました」は、日常会話ではよく使われる言葉ですが、ビジネスシーン、特に電話応対では、避けるべき表現です。「了解」には、「相手の事情や状況を理解し、承知した」という意味がありますが、敬意が十分に伝わらない可能性があります。
お客様や目上の人に対しては、「承知いたしました」または「かしこまりました」を使うのが適切です。「承知いたしました」は、「承知」に丁寧語の「いたしました」を付けた形で、相手に敬意を示すことができます。「かしこまりました」は、「かしこまる」に丁寧語の「ました」を付けた形で、より丁寧な印象を与えられます。
例えば、お客様から「〇〇の件、お願いします」と言われた場合、「了解しました」ではなく、「承知いたしました。〇〇の件、確かに承りました」と答えるのが適切です。
また、上司から「〇〇の資料を作成しておいて」と言われた場合、「了解しました」ではなく、「かしこまりました。〇〇の資料、作成いたします」と答えるのが適切です。
「了解しました」は、同僚や部下に対して使う分には問題ありません。しかし、お客様や目上の人に対して使うと、失礼な印象を与えてしまう可能性があるため、注意が必要です。状況に応じて、「承知いたしました」や「かしこまりました」を使い分けるようにしましょう。つまり、時と場合によって「了解しました」は使い分ける必要があり、相手を不快にさせない配慮が重要です。
二重敬語になってない?正しい敬語の使い方を再確認
二重敬語とは、一つの言葉に対して、同じ種類の敬語を二重に使ってしまうことです。例えば、「おっしゃられる」は、「言う」の尊敬語「おっしゃる」に、さらに尊敬の助動詞「れる」を付けた形で、二重敬語になります。正しくは、「おっしゃる」または「言われる」です。
二重敬語は、丁寧すぎる印象を与え、かえって不自然に聞こえてしまうことがあります。また、敬語を正しく使えていないという印象を与えてしまう可能性もあります。電話応対では、特に注意が必要です。
よくある二重敬語の例としては、
- 「おっしゃられる」(誤)→「おっしゃる」(正)または「言われる」(正)
- 「ご覧になられる」(誤)→「ご覧になる」(正)
- 「お越しになられる」(誤)→「お越しになる」(正)または「いらっしゃる」(正)
- 「お伺いさせていただきます」(誤)→「伺います」(正)
などがあります。
例えば、お客様に「〇〇様は、何とおっしゃられましたか?」と尋ねるのは、二重敬語です。正しくは、「〇〇様は、何とおっしゃいましたか?」または「〇〇様は、何と言われましたか?」です。
また、お客様に「〇〇の資料をご覧になられましたか?」と尋ねるのも、二重敬語です。正しくは、「〇〇の資料をご覧になりましたか?」です。
補足すると、文化庁の「敬語の指針」では、「お/ご~くださる」「お/ご~いただく」など、一部の表現を、習慣として二重敬語と認めています。しかし、原則としては、二重敬語は避けるべきです。正しい敬語の使い方を再確認し、自然で、相手に失礼のない言葉遣いを心がけましょう。
二重敬語は、自分では気づきにくいものです。日頃から、自分の言葉遣いを意識し、正しい敬語を使えるように努めましょう。さて、次は、言葉の言い換えで、さらに表現力をレベルアップさせる方法について見ていきましょう。
言い換えでレベルアップ。より洗練された表現をマスター
電話応対では、同じ言葉を繰り返すよりも、別の言葉に言い換えることで、より洗練された、相手に好印象を与えられます。
例えば、「わかりました」を繰り返すのではなく、「承知いたしました」「かしこまりました」「お受けいたしました」など、状況に応じて言い換えることができます。
また、「少々お待ちください」を繰り返すのではなく、「恐れ入りますが、少々お待ちいただけますでしょうか」「ただいま、〇〇(担当者名)にかわりますので、少々お待ちください」「お待たせして申し訳ございません。少々お待ちください」など、状況に応じて言い換えることができます。
さらに、「できません」という否定的な表現を、「いたしかねます」「できかねます」「難しい状況です」「ご希望に沿いかねます」など、より丁寧な表現に言い換えることができます。例えば、「〇〇はできません」と言う代わりに、「〇〇は、あいにく、いたしかねます」と言う方が、相手に与える印象が柔らかくなります。
具体的な例を挙げてみましょう。お客様から、「〇〇の商品を送ってほしい」と言われた場合、「〇〇の商品は、現在、取り扱っておりません」と答えるよりも、「〇〇の商品は、あいにく、現在、取り扱いを終了しております」と答える方が、より丁寧な印象を与えられます。
もう一つ例を挙げます。お客様から、「〇〇の件、すぐに調べてほしい」と言われた場合、「すぐにはできません」と答えるよりも、「〇〇の件、至急確認いたしますが、少々お時間をいただけますでしょうか」と答える方が、相手の要望に寄り添う姿勢を示せます。
ちなみに、「なるほど」という言葉も、電話応対では避けるべき表現です。「なるほど」は、相手の意見を評価するようなニュアンスが含まれているため、お客様や目上の人に対して使うと、失礼な印象を与えてしまう可能性があります。「なるほど」の代わりに、「さようでございますか」「おっしゃる通りでございます」などを使うようにしましょう。
言葉の言い換えは、電話応対だけでなく、ビジネスシーン全般で役立つスキルです。より洗練された表現をマスターし、相手に好印象を与えられるようにしましょう。ですから、日頃から、意識して言葉の言い換えを練習し、表現の幅を広げてください。
まとめ
新卒社員向け電話応対の言葉遣い完全マスター、いかがでしたでしょうか。今回は、電話応対の基本から、敬語の種類と使い分け、よく使うフレーズ、クッション言葉、そして、よくある間違いと改善策まで、幅広く解説しました。電話応対は、会社の顔としてお客様と接する大切な仕事です。正しい言葉遣いを身につけ、自信を持って電話応対に臨んでください。今回の記事を参考に、あなたの電話応対スキルが向上することを願っています。そして、お客様との良好な関係を築き、ビジネスを成功へと導いてください。

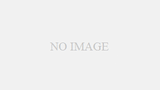
コメント