会社の電話を受ける時、緊張してうまく対応できない…そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。特に新入社員の方や、電話対応に慣れていない方にとっては、電話の受け答えは大きな壁に感じるかもしれません。このブログ記事では、電話を受ける際の具体的な手順から、担当者不在時の対応、スムーズな取次ぎ方法、伝言の受け方まで、実践的なテクニックを詳しく解説します。この記事を読めば、あなたも自信を持って電話対応できるようになるでしょう。
電話対応の基本ステップ:これであなたも電話マスター
名乗り方:第一印象を良くする3つのポイント
電話対応の第一歩は、名乗り方です。名乗り方次第で、相手に与える印象は大きく変わります。ここでは、好印象を与える名乗り方のポイントを3つご紹介します。
- 明るくハキハキとした声で名乗る: 声のトーンは、相手に与える印象を大きく左右します。「株式会社〇〇の△△です」と、明るくハキハキと名乗りましょう。例えば、朝一番の電話であれば、少し高めのトーンで元気よく名乗ることで、相手に爽やかな印象を与えられます。
- 会社名と部署名、氏名を省略せずに名乗る: 会社名、部署名、氏名を省略せずに名乗ることで、相手に安心感を与え、スムーズなコミュニケーションに繋がります。例えば、「〇〇株式会社 営業部の△△です」のように、所属部署を明確に伝えることで、相手は誰に繋げば良いのかを判断しやすくなります。
- 「お電話ありがとうございます」の一言を添える: 名乗りの後に「お電話ありがとうございます」の一言を添えることで、相手に感謝の気持ちを伝え、丁寧な印象を与えます。例えば、取引先からの電話であれば、「いつもお世話になっております。〇〇株式会社 営業部の△△です」のように、状況に応じた挨拶を付け加えることで、より丁寧な対応になります。
これらのポイントを意識するだけで、電話の第一印象は格段に良くなります。最初は緊張するかもしれませんが、練習を重ねることで自然とできるようになります。
挨拶:相手に安心感を与える魔法の言葉とは
名乗りの後の挨拶も、電話対応において非常に重要な要素です。適切な挨拶は、相手に安心感を与え、その後のコミュニケーションを円滑に進めるための土台となります。
基本的な挨拶としては、「お電話ありがとうございます」や「いつもお世話になっております」などがあります。これらの挨拶は、相手への感謝の気持ちを表すとともに、丁寧な印象を与えます。例えば、初めて電話をかけてきた相手には、「お電話ありがとうございます」と伝え、以前から取引のある相手には、「いつもお世話になっております」と伝えるなど、状況に応じて使い分けましょう。
さらに、時間帯に応じた挨拶を付け加えることも効果的です。午前中であれば「おはようございます」、午後であれば「こんにちは」といった挨拶を添えることで、より自然な会話の流れを作ることができます。例えば、午前中に電話を受けた場合は、「おはようございます。〇〇株式会社の△△です。お電話ありがとうございます」といった具合です。
また、相手の名前が分かっている場合は、「〇〇様、いつもお世話になっております」のように、名前を呼ぶことで、より親近感を与えることができます。ただし、初めて電話をかけてきた相手に対しては、名前を呼ぶのは避けましょう。
挨拶は、単なる形式的なものではなく、相手との関係性を築くための重要なコミュニケーションツールです。状況に応じた適切な挨拶を心がけることで、電話対応の質を向上させることができます。
用件の聞き取り:スムーズな会話に繋げる聞き上手テクニック
用件の聞き取りは、電話対応において最も重要なスキルの1つです。相手の話を正確に理解し、適切な対応をするためには、聞き上手になる必要があります。
まず、相手の話を遮らずに最後まで聞くことが大切です。相手が話している途中で口を挟んだり、自分の意見を言ったりすることは避けましょう。例えば、相手が用件を話し始めたら、相槌を打ちながら、最後までしっかりと耳を傾けます。相手が話し終わってから、質問や確認をするようにしましょう。
次に、相手の話の要点を把握するように努めましょう。相手の話が長くなったり、話が逸れたりする場合でも、落ち着いて話を聞き、何が一番重要なポイントなのかを見極めることが大切です。例えば、相手の話を聞きながら、「〇〇についてのお問い合わせですね」「〇〇の件で、△△様にお繋ぎすればよろしいでしょうか」など、頭の中で要点を整理しながら聞くと、よりスムーズに理解できます。
また、不明な点や聞き取りにくい点があった場合は、遠慮せずに質問しましょう。「恐れ入りますが、もう一度おっしゃっていただけますか」「〇〇について、もう少し詳しく教えていただけますか」など、丁寧な言葉遣いで質問することで、相手に不快感を与えることなく、正確な情報を得ることができます。例えば、相手の声が小さくて聞き取りにくい場合は、「恐れ入りますが、お電話が少し遠いようです」と伝えることで、相手に状況を理解してもらい、改善を促すことができます。
聞き上手になるためには、日頃から相手の話に耳を傾け、理解しようとする姿勢が大切です。電話対応だけでなく、普段のコミュニケーションにおいても、聞き上手になることを意識することで、人間関係を円滑にすることができます。それでは、スムーズな電話取次ぎの基本について、詳しく見ていきましょう。
電話取次ぎの基本:スムーズな取次ぎを実現するには
担当者への取次ぎ:確認事項と伝え方のコツ
電話の取次ぎは、単に担当者に電話を回すだけでなく、いくつかの確認事項と伝え方のコツがあります。これらを意識することで、よりスムーズで確実な取次ぎが可能になります。
まず、担当者の名前と部署名を正確に確認しましょう。同姓同名の社員がいる場合や、部署名が曖昧な場合は、相手に失礼のないように丁寧に確認することが大切です。例えば、「恐れ入りますが、〇〇部の△△でございますか」といった具合に確認します。
次に、担当者が在席しているかどうかを確認します。担当者が不在の場合は、その旨を相手に伝え、伝言を受けるか、折り返し連絡をするかを確認します。例えば、「申し訳ございません。△△はただいま席を外しております。伝言を承りましょうか、それとも折り返しご連絡いたしましょうか」といった具合に対応します。
担当者が在席している場合は、相手に用件を簡単に確認し、担当者に伝えます。この際、相手の名前と会社名も忘れずに伝えましょう。例えば、「〇〇株式会社の△△様から、〇〇についてのお電話です」と伝えることで、担当者はスムーズに電話に出ることができます。
また、電話を保留にする際は、相手にその旨を伝え、了解を得てから保留にしましょう。「少々お待ちいただけますでしょうか」と一言添えることで、相手に丁寧な印象を与えます。保留時間が長くなる場合は、「お待たせして申し訳ございません」と、途中で状況を伝えることも大切です。
補足すると、内線電話を使用する場合は、担当者の内線番号を正確に確認し、転送ミスを防ぐようにしましょう。内線番号を間違えると、相手に迷惑をかけるだけでなく、会社の信頼を損なう可能性があります。
担当者不在時の対応:失礼のない対応を心がけよう
担当者が不在の場合の対応は、会社の印象を左右する重要なポイントです。相手に失礼のないよう、丁寧かつ適切な対応を心がけましょう。
まず、担当者が不在であることを、丁寧な言葉遣いで伝えましょう。「申し訳ございません。〇〇はただいま席を外しております」「あいにく〇〇は本日休みをいただいております」など、状況に応じた適切な表現を使います。例えば、担当者が会議中の場合は、「〇〇はただいま会議中でございます」と伝えることで、相手に状況を理解してもらうことができます。
次に、相手に伝言を受けるか、折り返し連絡をするかを確認します。相手が伝言を希望する場合は、伝言内容を正確に記録し、担当者に伝えます。折り返し連絡を希望する場合は、相手の連絡先と都合の良い時間帯を確認し、担当者に伝えます。例えば、「よろしければ伝言を承りますが、いかがいたしましょうか」「〇〇から折り返しご連絡差し上げてもよろしいでしょうか」といった具合に確認します。
また、担当者の帰社時間や連絡が取れる時間帯が分かっている場合は、相手に伝えると親切です。「〇〇は〇時に帰社予定です」「〇〇には〇時以降であれば連絡が取れます」など、具体的な情報を伝えることで、相手は安心することができます。例えば、担当者が外出中で、携帯電話に連絡がつく場合は、「〇〇は外出中ですが、携帯電話に連絡がつきます。いかがいたしましょうか」と伝えることもできます。
担当者不在時の対応は、相手への配慮が何よりも大切です。相手の状況や気持ちを考え、丁寧かつ適切な対応を心がけることで、会社の信頼を高めることができます。
クレーム電話の取次ぎ:冷静に対応するためのポイント
クレーム電話の取次ぎは、特に慎重な対応が求められます。相手は感情的になっている場合が多く、対応を間違えると、事態を悪化させる可能性があります。
まず、相手の話を冷静に、最後まで聞くことが大切です。相手が感情的になっている場合でも、途中で口を挟んだり、反論したりすることは避けましょう。相槌を打ちながら、相手の言葉に耳を傾け、何に対して怒っているのか、何を求めているのかを正確に把握するように努めます。例えば、相手が「〇〇が悪い」と何度も繰り返している場合は、「〇〇について、ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません」と、相手の気持ちに寄り添う言葉を伝えましょう。
次に、相手の怒りを鎮めるために、謝罪の言葉を述べましょう。「この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」「ご不便をおかけし、大変申し訳ございません」など、丁寧な言葉遣いで謝罪することで、相手の気持ちを落ち着かせることができます。例えば、商品の不具合に関するクレームの場合は、「製品の不具合により、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」と謝罪します。
そして、担当者に状況を正確に伝え、迅速に対応するように依頼します。担当者に伝える際は、相手の名前、会社名、連絡先、クレームの内容、相手の要望などを具体的に伝えましょう。例えば、「〇〇株式会社の△△様から、〇〇という商品に不具合があったと、お怒りのお電話です。至急、対応をお願いします」と伝えることで、担当者は迅速かつ適切な対応をすることができます。
クレーム電話は、会社にとって改善の機会でもあります。相手の意見を真摯に受け止め、今後のサービス向上に繋げることが大切です。次に、伝言の受け方について見ていきましょう。伝言を正確かつ漏れなく伝えるためには、いくつかのポイントがあります。
伝言の受け方:正確かつ漏れなく伝えるために
伝言メモの書き方:5W1Hを意識しよう
伝言メモは、電話の内容を正確に記録し、担当者に伝えるための重要なツールです。伝言メモを書く際は、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識することで、必要な情報を漏れなく記録することができます。
- When(いつ): 電話を受けた日時を正確に記入します。
- Who(誰が): 電話をかけてきた相手の会社名、部署名、氏名を記入します。
- Whom(誰に): 伝言の宛先となる担当者の氏名を記入します。
- What(何を): 伝言の内容を簡潔に記入します。
- Why(なぜ): 電話をかけてきた理由や背景を記入します。
- How(どのように): 今後の対応(折り返し連絡、至急対応など)を記入します。
これらの情報を、箇条書きで分かりやすく記入することがポイントです。例えば、「〇月〇日 〇時〇分 〇〇株式会社 △△様より 〇〇様宛て お電話あり。〇〇の件で至急連絡が欲しいとのこと。」といった具合に記入します。
また、伝言メモには、自分の名前と連絡先も記入しておきましょう。担当者が伝言内容について質問したい場合に、すぐに連絡を取ることができます。例えば、伝言メモの最後に、「伝言者:〇〇(内線〇〇)」と記入しておきます。
伝言メモは、会社の共有スペースに保管したり、担当者のデスクに置いたりするなど、担当者がすぐに確認できる場所に置くようにしましょう。
伝言内容の復唱:聞き間違いを防ぐために
伝言内容の復唱は、聞き間違いを防ぎ、正確な情報を伝えるために非常に重要です。相手から伝言内容を聞き取った後、必ず復唱して確認するようにしましょう。
復唱する際は、「〇〇株式会社の△△様から、〇〇様宛てに、〇〇についてのお電話で、〇〇してほしいということでよろしいでしょうか」といった具合に、5W1Hを意識しながら、相手に確認します。例えば、相手が「〇〇の件で至急連絡が欲しい」と言った場合は、「〇〇の件で至急連絡が欲しいということでよろしいでしょうか」と復唱します。
もし、聞き取りにくい点や不明な点があった場合は、遠慮せずに質問しましょう。「恐れ入りますが、〇〇の部分をもう一度おっしゃっていただけますか」「〇〇について、もう少し詳しく教えていただけますか」など、丁寧な言葉遣いで質問することで、相手に不快感を与えることなく、正確な情報を得ることができます。
復唱は、単なる確認作業ではなく、相手とのコミュニケーションを円滑にするための重要なプロセスです。復唱することで、相手は自分の話が正しく伝わっていることを確認でき、安心することができます。
伝言を伝えるタイミング:相手に配慮した伝え方
伝言を伝えるタイミングも、電話対応において重要な要素です。担当者が忙しい時や、席を外している時に伝言を伝えても、すぐに確認してもらえない可能性があります。
担当者が席に戻ってきたら、なるべく早く伝言を伝えましょう。ただし、担当者が他の電話中や、来客対応中の場合は、少し時間をおいてから伝えるようにします。例えば、担当者が電話中の場合は、「お電話中失礼いたします。〇〇株式会社の△△様から伝言がございます」と、メモを渡すなど、状況に応じた対応をしましょう。
また、伝言の内容によっては、緊急度が高い場合もあります。至急対応が必要な伝言の場合は、担当者の状況を確認し、すぐに伝えられるように準備しておきましょう。例えば、「〇〇株式会社の△△様から、〇〇の件で至急連絡が欲しいとのことです」と、伝えることで、担当者はすぐに対応することができます。
伝言を伝える際は、口頭で伝えるだけでなく、伝言メモを渡すようにしましょう。口頭で伝えるだけでは、聞き間違いや伝え漏れが発生する可能性があります。伝言メモを渡すことで、担当者は正確な情報を確認することができます。
伝言を伝えるタイミングは、相手への配慮が何よりも大切です。相手の状況を考え、適切なタイミングで伝えることで、スムーズなコミュニケーションに繋がります。続いては、電話対応に苦手意識を持つ方、特に新卒者の方に向けて、よくある疑問とその解決策をまとめました。
電話対応でよくある疑問を解決
電話が苦手意識を克服する方法
新卒者や、電話対応に慣れていない方にとって、電話対応は大きな不安要素の一つかもしれません。しかし、電話対応の苦手意識は、適切な方法で克服することができます。
まず、電話対応の練習を重ねることが大切です。会社の先輩や同僚に協力してもらい、ロールプレイング形式で練習することで、実際の電話対応に近い状況を体験することができます。例えば、先輩に電話をかけてもらい、自分が電話を受ける練習をしたり、自分が電話をかける練習をしたりすることで、徐々に慣れていくことができます。
次に、電話対応のマニュアルや、よくある質問集などを参考に、基本的な知識を身につけましょう。会社の電話対応マニュアルには、名乗り方、挨拶、取次ぎ方法、伝言の受け方など、基本的な手順が記載されています。また、よくある質問集には、電話対応でよくある質問とその回答がまとめられています。これらの情報を参考にすることで、自信を持って電話対応できるようになります。
さらに、自分の電話対応を録音し、聞き直すことも効果的です。自分の声のトーンや話し方、言葉遣いなどを客観的に評価することで、改善点を見つけることができます。例えば、録音した自分の声を聞いて、「声が小さい」「早口になっている」「言葉遣いが丁寧でない」などの点に気づくことができれば、意識して改善することができます。
電話対応は、経験を積むことで必ず上達します。最初は緊張するかもしれませんが、積極的に電話対応に挑戦し、経験を積むことで、苦手意識を克服することができます。
敬語の使い分け:自信を持って話せるようになるには
電話対応では、正しい敬語を使うことが求められます。しかし、敬語には様々な種類があり、使い分けに迷うこともあるかもしれません。
敬語には、大きく分けて、尊敬語、謙譲語、丁寧語の3種類があります。
- 尊敬語: 相手の動作や状態を高めて、敬意を表す言葉です。「おっしゃる」「いらっしゃる」「ご覧になる」などがあります。
- 謙譲語: 自分の動作や状態をへりくだって、相手に敬意を表す言葉です。「申す」「伺う」「拝見する」などがあります。
- 丁寧語: 言葉遣いを丁寧にして、相手に敬意を表す言葉です。「です」「ます」「ございます」などがあります。
これらの敬語を、状況に応じて適切に使い分けることが大切です。例えば、相手に何かを尋ねる場合は、「〇〇についてお伺いしてもよろしいでしょうか」と謙譲語を使います。相手に何かを伝える場合は、「〇〇についてご説明いたします」と丁寧語を使います。相手の意見を聞く場合は、「〇〇様はどうお考えになりますか」と尊敬語を使います。
敬語の使い分けは、慣れるまで難しいかもしれませんが、練習を重ねることで自然とできるようになります。会社の先輩や上司の言葉遣いを参考にしたり、敬語に関する書籍やWebサイトを参考にしたりするのも良いでしょう。
また、普段から丁寧な言葉遣いを心がけることも大切です。友人や家族との会話でも、丁寧な言葉遣いを意識することで、敬語を自然に使えるようになります。
こんな時どうする?電話対応のQ&A集
電話対応をしていると、様々な状況に遭遇します。ここでは、電話対応でよくある質問とその回答をまとめました。
Q:相手の声が小さくて聞き取りにくい場合はどうすれば良いですか?
A:「恐れ入りますが、お電話が少し遠いようです。もう一度おっしゃっていただけますか」と、丁寧な言葉遣いで聞き返しましょう。
Q:相手が名乗らない場合はどうすれば良いですか?
A:「恐れ入りますが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか」と、丁寧な言葉遣いで尋ねましょう。
Q:担当者が不在の場合、相手にどのように伝えれば良いですか?
A:「申し訳ございません。〇〇はただいま席を外しております。よろしければ伝言を承りますが、いかがいたしましょうか」と、丁寧な言葉遣いで伝え、相手の意向を確認しましょう。
Q:電話中に保留にする場合は、どのように伝えれば良いですか?
A:「少々お待ちいただけますでしょうか」と、一言添えてから保留にしましょう。保留時間が長くなる場合は、「お待たせして申し訳ございません」と、途中で状況を伝えることも大切です。
Q:クレーム電話を受けた場合は、どのように対応すれば良いですか?
A:まず、相手の話を冷静に、最後まで聞きましょう。そして、相手の怒りを鎮めるために、謝罪の言葉を述べましょう。「この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」など、丁寧な言葉遣いで謝罪することが大切です。その後、担当者に状況を正確に伝え、迅速に対応するように依頼します。
これらのQ&Aは、あくまで一例です。電話対応では、様々な状況に遭遇するため、臨機応変な対応が求められます。しかし、基本的なマナーや言葉遣いを身につけていれば、落ち着いて対応することができます。最後にこれまでご紹介した内容を基に電話対応をマスターするための全体的な総括をします。
電話対応&取次ぎマスターガイド
電話対応の心構え:自信を持つことが大切
電話対応は、ビジネスシーンにおいて避けて通れない業務の一つです。しかし、電話対応に苦手意識を持つ方も少なくありません。電話対応をスムーズに行うためには、まず、自信を持つことが大切です。
自信を持つためには、電話対応の基本的なスキルを身につけることが重要です。名乗り方、挨拶、用件の聞き取り、取次ぎ、伝言の受け方など、基本的な手順を理解し、練習を重ねることで、自然と自信がついてきます。例えば、ロールプレイング形式で練習したり、自分の電話対応を録音して聞き直したりすることで、改善点を見つけ、スキルアップすることができます。
また、電話対応は、相手とのコミュニケーションであることを意識しましょう。電話の向こうには、必ず相手がいます。相手の気持ちを考え、丁寧な言葉遣いを心がけ、誠実に対応することで、相手との良好な関係を築くことができます。例えば、相手の名前を呼んだり、相手の状況を尋ねたりすることで、より親近感のあるコミュニケーションをすることができます。
さらに、電話対応は、会社の顔としての役割を担っていることを自覚しましょう。電話対応の良し悪しは、会社の印象を大きく左右します。丁寧で適切な電話対応は、会社の信頼を高め、顧客満足度向上に繋がります。例えば、明るくハキハキとした声で対応したり、相手の質問に丁寧に答えたりすることで、会社の印象を良くすることができます。
電話対応は、経験を積むことで必ず上達します。最初は緊張するかもしれませんが、積極的に電話対応に挑戦し、経験を積むことで、自信を持って対応できるようになります。
ビジネス電話のマナー:社会人としての基本
ビジネス電話には、社会人として守るべき基本的なマナーがあります。これらのマナーを守ることで、相手に不快感を与えることなく、スムーズなコミュニケーションをすることができます。
- 3コール以内に出る: 電話が鳴ったら、3コール以内に出るのがマナーです。3コール以上待たせてしまう場合は、「お待たせいたしました」と一言添えましょう。
- 明るくハキハキとした声で名乗る: 会社名、部署名、氏名を省略せずに、明るくハキハキと名乗りましょう。
- 丁寧な言葉遣いを心がける: 敬語を正しく使い、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
- 相手の話を最後まで聞く: 相手の話を遮らずに最後まで聞き、用件を正確に把握しましょう。
- 復唱確認をする: 相手の用件や伝言内容を復唱し、聞き間違いがないか確認しましょう。
- 電話を切る際は、相手が先に切るのを待つ: 電話を切る際は、「失礼いたします」と一言添え、相手が先に切るのを待ってから静かに切りましょう。
これらのマナーは、電話対応だけでなく、ビジネスシーン全般において重要なものです。日頃から意識することで、社会人としての信頼を高めることができます。
ちなみに、携帯電話を使用する場合は、周囲の状況に配慮しましょう。電車内や会議中など、通話が適切でない場所では、電源を切るか、マナーモードに設定しましょう。
電話対応スキルアップ:継続的な学習で差をつける
電話対応のスキルは、一度身につければ終わりではありません。継続的な学習によって、さらにスキルアップし、より質の高い電話対応をすることができます。
まず、自分の電話対応を定期的に振り返り、改善点を見つけるようにしましょう。自分の電話対応を録音して聞き直したり、先輩や同僚にフィードバックをもらったりすることで、客観的に自分の電話対応を評価することができます。例えば、「早口になっている」「言葉遣いが丁寧でない」などの点に気づくことができれば、意識して改善することができます。
次に、電話対応に関する書籍やWebサイトを参考に、新しい知識やテクニックを学びましょう。電話対応に関する情報は、様々な媒体で提供されています。これらの情報を参考にすることで、自分のスキルをさらに向上させることができます。例えば、敬語の使い方や、クレーム対応のテクニックなど、より専門的な知識を学ぶことができます。
さらに、電話対応の研修やセミナーに参加するのも効果的です。電話対応の専門家から直接指導を受けることで、より実践的なスキルを身につけることができます。例えば、ロールプレイング形式の研修に参加したり、グループワークを通じて他の参加者と意見交換したりすることで、新たな気づきを得ることができます。
電話対応のスキルアップは、日々の業務の中で意識して取り組むことが大切です。継続的な学習によって、電話対応のプロフェッショナルを目指しましょう。それでは最後にまとめです。
まとめ
この記事では、電話対応の基本ステップから、取次ぎ、伝言の受け方、新卒者向けのQ&A、そしてスキルアップの方法まで、幅広く解説しました。電話対応は、ビジネスシーンにおいて避けて通れない業務であり、その良し悪しは会社の印象を大きく左右します。しかし、適切な知識とスキルを身につけ、練習を重ねることで、誰でも自信を持って電話対応できるようになります。この記事で紹介した内容を参考に、ぜひ電話対応のスキルアップに挑戦してみてください。あなたの電話対応が、会社全体のコミュニケーションを円滑にし、ビジネスを成功に導く鍵となるはずです。

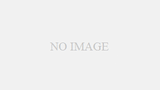
コメント